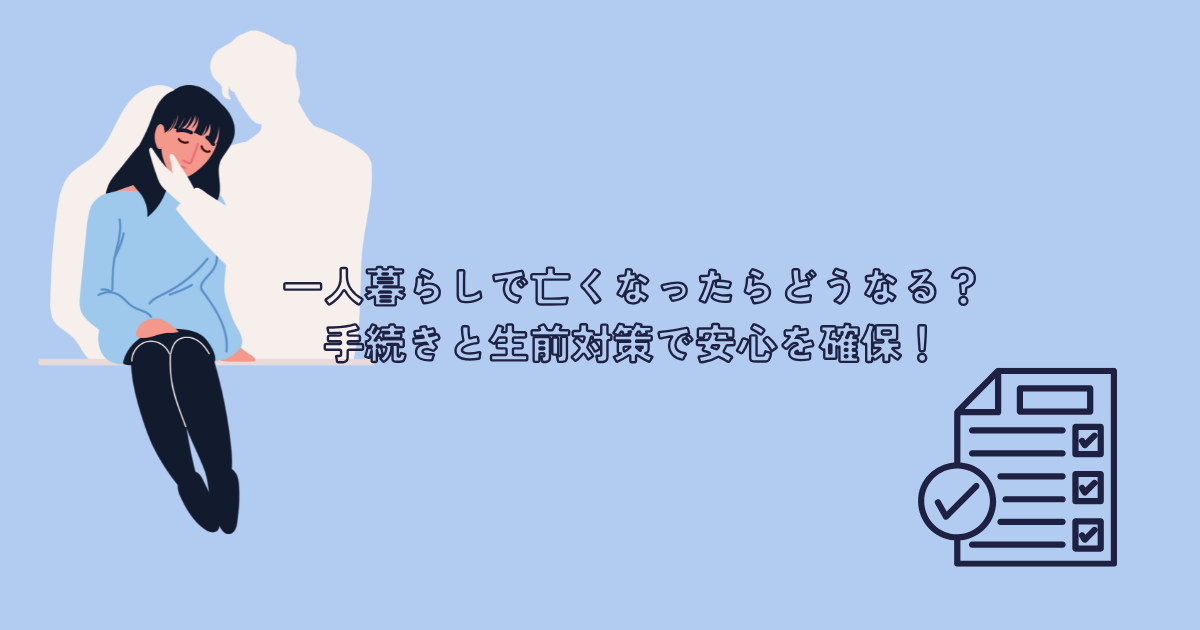 一人暮らしの高齢者の方にとって、将来の不安は大きな課題です。
一人暮らしの高齢者の方にとって、将来の不安は大きな課題です。
特に、もしもの時に備えて、どのような手続きが必要なのか、誰に相談すればいいのか、といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、一人暮らしの方が亡くなられた場合の手続きについて、分かりやすく解説します。
また、ご自身でできる生前対策についてもご紹介しますので、不安の解消にお役立てください。
高齢の一人暮らしの方々が安心して暮らせるよう、少しでもお役に立てれば幸いです。
亡くなられたことが確認されたら、まず死亡届を提出する必要があります。
死亡届は、医師から交付される死亡診断書(または死体検案書)とセットになっていることが多いです。
亡くなられた日から7日以内に、亡くなられた方の本籍地または死亡地を管轄する市区町村役所に提出しましょう。
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。
この火葬許可証は、火葬を行う際に必要となります。
死亡届の提出後、葬儀社の手配を行いましょう。
葬儀の規模や形式、費用などは、ご遺族の意向や故人の希望などを考慮して決定します。
葬儀社には、葬儀に関する手続きや費用について相談することができます。
亡くなられた方が契約していた賃貸契約、公共料金(電気、ガス、水道、電話など)、携帯電話、インターネット、NHK受信料、クレジットカードなどの契約は、速やかに解約する必要があります。
解約手続きには、契約内容によって必要な書類や手続き方法が異なる場合がありますので、各事業者へ確認しましょう。
未払い料金の精算も忘れずに行いましょう。
故人の住居の片付け、遺品の整理・処分を行います。
遺品の中には、故人の思い出が詰まった大切な品々も含まれています。
時間や体力が不足している場合は、遺品整理業者に依頼するのも一つの方法です。
亡くなられた方が年金や健康保険に加入していた場合は、それぞれの機関に資格喪失の手続きが必要です。
年金の場合は「年金受給権者死亡届」、健康保険の場合は「資格喪失届」を提出します。
手続きに必要な書類や期限は、年金事務所や健康保険組合によって異なりますので、事前に確認しましょう。
国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費の支給制度もありますので、自治体に確認してみましょう。

死後事務委任契約とは、亡くなった後の手続きを、事前に委任する契約です。
信頼できる家族や友人、または専門家(司法書士、行政書士など)に、死亡届の提出、葬儀の手配、遺品整理、各種契約の解約など、様々な事務手続きを委任することができます。
ご自身の希望する葬儀方法などを具体的に記載しておくことも可能です。
1: 委任内容の例
死亡届の提出
葬儀の手配
銀行口座の解約
賃貸契約の解約
生命保険金受取手続き
遺品整理
債権・債務の精算
2: 契約相手について
信頼できる人物を選ぶことが重要です。
家族や親戚だけでなく、弁護士や司法書士などの専門家も候補となります。
遺言書を作成することで、ご自身の財産をどのように相続させるか、希望通りに決定できます。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った遺言書を選びましょう。
1: 遺言の種類と選び方
自筆証書遺言:全て自筆で作成する必要があるため、作成に手間がかかりますが、費用はかかりません。
公正証書遺言:公証役場で作成するため、法的効力が強く、紛争リスクが低い反面、費用がかかります。
秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にすることができますが、証人の立ち会いが必要で、内容の確認が難しい点がデメリットです。
2: 専門家への相談
遺言書の作成は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
専門家のアドバイスを受けることで、より適切な遺言書を作成することができます。

一人暮らしの方が亡くなられた場合、多くの手続きが必要になります。
今回は、死亡届の提出、葬儀の手配、各種契約の解約、遺品整理、年金・健康保険の手続きなど、具体的な手続き内容と流れを解説しました。
これらの手続きは、ご家族や親族に大きな負担となる可能性があります。
そのため、生前に死後事務委任契約を締結したり、遺言書を作成しておくことは、ご自身にとっても、ご家族にとっても、安心につながります。